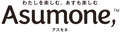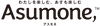精神科医・和田秀樹さんに聞く「シニア世代が趣味を持つべき3つの理由」



なぜシニア世代に「趣味」が必要なの?
みなさんは、今夢中になっていることや、この先やってみたいことはありますか?
「若い頃ならチャレンジしたけれど…」とか「ずっと働いてきたから、退職後は家でゴロゴロしたい」「もう年だし、今さら新しいことを始めるのも面倒」という方もいるかもしれません。
そんなあなたは老け込みリスクが高いので要注意!
「定年後や子どもが独立して母親業を終えた後にガクッと年を取ったという人によく出会います。前頭葉が老化している上に、役割や緊張感から解き放たれて気持ちに張りがない状態が続くと、急に老け込んでしまうのです」と話すのは、シニアの生きがいについて多くの著書がある精神科医の和田秀樹さん。和田さんによると、老け込み防止策として趣味を持つことが有効なのだそう。
なぜ趣味をもつと老け込まずにいられるのか。理由は大きく3つあると言います。
■理由1:新たな刺激で脳が活性化する



仕事や子育てをしていると、自分の知らない新たな情報に触れるほか、周りの人とコミュニケーションを図ったり、想定外のトラブルに対応したりするなどして、そのたびに脳は活発に働きます。
ところが、退職したり子離れしたりした後に人に会わず家でゴロゴロするだけで脳への刺激がない状態が続くと、大脳の前方部分にある思考、意欲、感情、理性などをつかさどる前頭葉がそうでなくても老化しているのに、それが一気に進行。「行動することが億劫になり、動かないとどんどん運動機能が低下し、脳の老化はさらに進み……と負の連鎖が続いてしまいます。この老け込みの悪循環を阻止するために、趣味による刺激は有効です」
■理由2:生活に張り合いやメリハリが生まれ、心が若返る
趣味を持つと、スキルアップしようという意欲や好奇心が湧き、心も体もイキイキしてきます。「現代の心理療法では『行動を変えれば心も変わってくる』という行動療法がトレンドになってきました。心の若さを保ちたいなら、趣味の活動のためにおしゃれをしたり、若い世代と交流したり……。若々しい活動をしていれば、心はどんどん若返っていきます」
■理由3:自分が楽しんでいれば、周囲も楽しい気持ちになる
趣味があると育てた野菜をご近所さんにおすそ分けしたり、撮影した写真をプレゼントしたり、育てた花がご近所さんの癒やしになっていたり、自分が楽しんでやっていることが結果的に周りに喜ばれるなんていうこともあります。「楽しそうにしている人を見ていると、楽しい気持ちになってきますよね。『幸せな気持ち』は不思議と連鎖するものです」と和田さんは言います。「自分がご機嫌でいることでさらに周りもハッピーにできるなんて、ステキなことじゃないですか」
特に男性は趣味を持つべし!その理由とは?



和田さんは「特に男性は意識的に趣味を持つように心がけてほしい」と指摘します。
女性は閉経後、女性ホルモン(エストロゲン、プロゲステロン)が減る一方で、男性ホルモン(テストステロン)が増えて活動的になる傾向にあり、年齢を重ねても趣味を持ってアクティブに活動する人が多くなります。かたや男性は、年齢を重ねると男性ホルモンが減少して活力が落ちてくる傾向にあり、人に会うのが億劫になり家にこもりがちな人が増えてきがちです。
「人に会わずに引きこもってしまうと、前述したように老け込む一方になってしまいます。男性はなるべく趣味を持ち、外や人とのつながりを持ち続けるようにしましょう」
シニアの趣味ランキング【男性編】
では一体、シニア世代のみなさんはどんな趣味を楽しんでいるのでしょう。総務省統計局の「令和3年社会生活基本調査」の結果から、65歳以上の趣味を男女別にランキング形式で見ていきます。
※図表内のパーセンテージは、その趣味へ過去1年間(該当期間:令和2年10月20日~令和3年10月19日)に参加した人の割合(行動率)を表しています。
まずは男性の結果から。



1位の「園芸、庭いじり、ガーデニング」と2位の「映画館以外での映画鑑賞」が趣味への参加率30%以上と高い結果に。「読書」や「CD、スマホなどによる音楽鑑賞」「日曜大工」もメジャーな趣味として親しまれているようです。また、「スマホなどによるゲーム」も趣味としてシニア世代にも浸透してきているようです。
シニアの趣味ランキング【女性編】
続いて、女性の結果を見ていきましょう。



TOP3は男性と同様のラインナップ。「園芸、庭いじり、ガーデニング」が最も多く、趣味への参加率は43.3%と男性よりも高い結果に。次いで「読書」、「映画館以外での映画鑑賞」と続きます。男性の結果との違いとしては、「料理」「編み物・手芸」「和裁・洋裁」がランクイン。家事として日常的に行っている料理や裁縫を、「趣味」として楽しむ人がいることが伺えます。
趣味で「当たり前が通用しない世界」の体験を



結果を見ると、TOP10には読書や映画鑑賞といった"ひとりで楽しむ系"のものが多く並んでいます。和田さんは「自分だけで没頭する趣味は想定内のことが多く、今ひとつ刺激が弱い」と指摘します。
一方で男女ともに1位にランクインした「園芸、庭いじり、ガーデニング」は相手が植物だと、思うように育たない、失敗するといったこともしばしば。また、屋外に出て作業をすると「きれいですね」「何の花ですか」と声を掛けられるコミュニケーションも生まれるため、前頭葉への刺激が多くおすすめだそう。
和田さんは、「60歳を過ぎたら日常とは違う環境に足を運んだり、身を置いたりすることで『想定しなかったこと』『当たり前が通用しないこと』を体験するよう心掛けてみてほしい」と話します。
「自分に合う趣味」はどうやって見つけたらいい?



では、自分に合った趣味はどうしたら見つかるのでしょう。和田さんは「余計なことは考えずに、なんとなく興味を持ったことをとりあえず試してみることが大事」とアドバイスします。
「『始めたからには何かしら成果を出さないといけない』という風潮がありますが、やってみて違うなと思ったら、また次の新しいことをやってみたらいいんです。三日坊主は決して恥ずかしいことではありません。『嫌われる勇気』で知られる心理学者のアドラーは、『人目の奴隷になるな』という言葉を残しています。子どもの頃に好きだったミニカーにまたはまってみたっていい。要は何かに興味をもつ、好奇心をもつこと自体が大切なのです」
まとめ:60代からの趣味選びの3つのポイント
■「当たり前が通じない世界」が体験できるものを選ぶ
■他人の目は気にせず、自分がやってみたいかどうかを基準に選ぶ
■新たに興味が湧くものがなかったら、昔好きだったものに立ち返ってみる
厚労省の「簡易生命表」(令和5年)によると、65歳の男性の平均余命は約19年、女性は約24年。「今から体や脳を使い続けていけば、生きている間に元気で活動できる期間を長く延ばせます。仕事をリタイアした後も、夢中になれる趣味を持って刺激ある毎日を送ることをおすすめします」(和田さん)

和田秀樹さんプロフィール
精神科医、和田秀樹こころと体のクリニック院長。1960年、大阪府生まれ。東京大学医学部卒業。高齢者専門の精神科医として、30年以上にわたり、高齢者医療の現場に携わる。『70歳が老化の分かれ道』(詩想社新書)、『80歳の壁』(幻冬舎新書)、『70代は男も女もやりたいことをおやりなさい』(KADOKAWA刊)、『シン・老人力』(小学館刊)など著書多数。